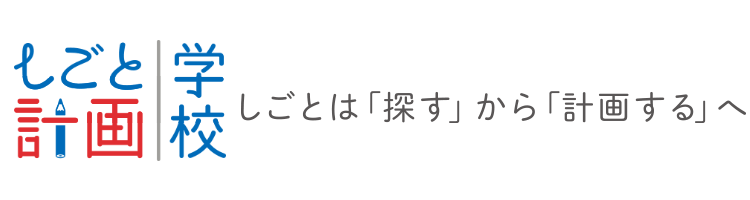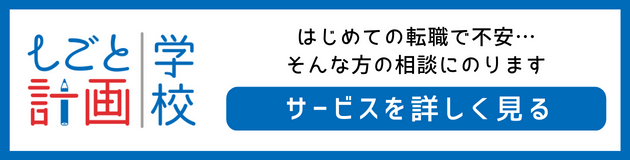パートで働く主婦ならば誰もが気になる「扶養内」というキーワード。
扶養に入るためにはどんな条件があるのかご存知ですか?
パートで働くなら一度は勉強しておきたい、パート主婦が夫の扶養内で働くためのポイントについて徹底解説します!
扶養内で働くとは

パートで働くなら「扶養内」という言葉はよく耳にするのではないでしょうか。
扶養は大きく分けて「所得税における扶養」と「社会保険における扶養」の2種類。
「所得税における扶養」では、所得税の控除を受けることができ、扶養する人の所得税が少し安くなります。
この控除は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類があり、どちらが適応されるかは、扶養される人の収入によって決められます。
法改正により、2018年からは控除額が扶養する人の収入によって変わるようになったほか、配偶者特別控除の適応範囲が拡大したことにより控除が受けやすくなりました※1。
また、「社会保険における扶養」では、健康保険と厚生年金保険において、扶養する人と同じ保険に入ることができたり、保険料が免除されたりします。
金銭的なメリットから、夫の扶養内で働きたいと思う主婦の方も多いのではないでしょうか。
一方で、扶養に入るには一定の条件をクリアする必要が。その条件は所得税と社会保険で異なります。
所得税における扶養
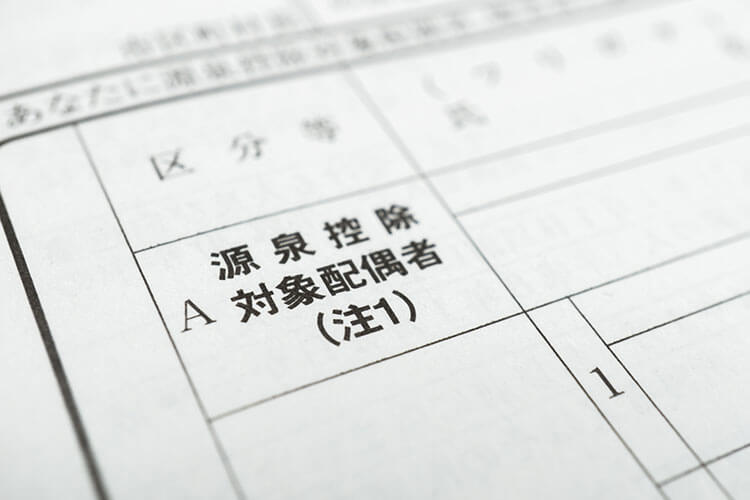
配偶者控除の対象となる条件
控除の対象となるための条件は次の4つ。全てに当てはまっていれば、控除の対象となります※2。
- 民法上の配偶者であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得が48万円以下であること※9。
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと。
なんだか小難しい感じですね。分かりやすいように順を追ってご説明します。
1.民法上の配偶者であること
パート主婦の場合、民法上の配偶者とは婚姻関係にあることを指します。内縁関係の場合は対象にはなりません。
夫の扶養に入る場合、扶養される妻の収入等をもとに、夫の所得税が控除の対象となるかどうか決まります。
2.納税者と生計を一にしていること
「生計を一にしている」とは、夫婦の収入を一緒に使って生活している状態を指します。
パート主婦の場合、主に夫の収入で生活している状態になることが多いでしょう。
夫は夫が得た収入のみ、妻は妻が得た収入のみを使って独立した生活している場合は認められません。
一方で、夫の単身赴任などで別居状態にあっても、夫と妻が1つの収入を分けて生活していれば「生計を一にしている」と認められます。
3.年間の合計所得が48万円以下であること
パート主婦が夫の扶養に入る場合、妻の合計所得が48万円以下であれば、夫は控除の対象になります※9。
合計所得とは、その年に得た収入から割り出した所得の合計金額です。
給与収入や不動産収入などの収入からそれぞれ所得を割り出し、その金額を合計します。
会社員などで収入が給与収入しかない場合は、給与収入から給与所得控除を引いて出た所得が合計所得になります。
給与収入が100万円の場合を例に計算してみましょう。
まずは給与所得控除を計算します。計算式は次の表のとおり※3 ※9。
| 給与収入 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円(最低55万円) |
| 180万円~360万円 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円~660万円 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円~850万円 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
主婦のパートでの年間の給与収入が100万円の場合、1番上の段の「収入金額×40%-10万円」で割り出します。
給与所得控除額=100万円×40%-10万円=30万円
給与所得控除額の最低額は55万円となっていますので、給与収入100万円の給与所得控除額は55万円です。
よって、合計所得は
給与収入100万円ー給与所得控除額55万円=45万円
合計所得が48万円以下ですので、パート主婦の年間の給与収入が100万円の場合、夫は配偶者控除の対象になります。
収入が給与収入のみの場合、給与収入103万円以下であれば合計所得が48万円以下となります。
48万円を少しでも超えてしまうと対象ではなくなってしまいますので、しっかり注意しましょう。
4.青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
青色申告者・白色申告者とは、自営業などの個人事業主のことを指します。
個人事業主の事業専従者とはつまり、従業員となっている状態のこと。
夫婦で自営業を行っている、または扶養に入る人が自営業を行っている場合は、控除の対象にはなりません。
一般的なパートをしている主婦は青色申告者・白色申告者の事業専従者ではありませんので、この条件はクリアできる場合が多いでしょう。
配偶者控除ではいくら控除される?

配偶者控除の対象となればいくら控除されるのでしょう。
控除される金額は扶養する人の合計所得によって異なります。
合計所得ごとの控除額は以下のとおり※2。収入が給与のみの場合の給与収入も合わせて記載しています※9。
| 扶養する人の 合計所得 |
扶養する人の 給与収入 |
控除額 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 1095万円以下 | 38万円 |
| 900万円~950万円 | 1095万円~1145万円 | 26万円 |
| 950万円~1000万円 | 1145万円~1195万円 | 13万円 |
控除を受ける夫の収入が給与のみの場合、年収1095万円以下であれば、控除は満額の38万円になります。
夫の合計所得が1000万円、年収1195万円を超える場合、控除は一切受けられません。
この控除は夫が支払う所得税に対して適応されます。
一方で、この時の扶養される妻の所得税は0円。
所得から課税所得を割り出し、所得税を計算するのですが、その際に基礎控除で所得から48万円が控除されます。
配偶者控除の対応となる合計所得が48万円の場合、所得が0円となり課税すべき所得がなくなるため、所得税も0円となるのです※4 ※9。
配偶者控除の対象額内で働けば、自身の所得税と扶養する人の所得税の2つでお得になりますね。
配偶者特別控除の対象となる条件

控除の対象となるための条件は次の6つ。全てに当てはまっていれば、控除の対象となります※5。
- 納税者本人のその年の合計所得が1000万円以下であること。
- 民事法上の配偶者であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと。
- 他の人の扶養に入っていないこと。
- 年間の合計所得が48万円を超えていて133万円以下であること※9。
条件の2~4に関しては配偶者控除と同じです。残りの条件について、順を追ってご説明します
1.納税者本人のその年の合計所得が1000万円以下であること
パート主婦が夫の扶養に入る場合、夫の合計所得が1000万円を超えると対象となれません。
給与収入のみの場合、合計所得が1000万になるのは年収1195万円の時なので、年収1195万円以下であれば対象となることできます※9。
5.他の人の扶養に入っていないこと
夫がすでに他の人の扶養に入っていると、妻は夫の扶養に入ることができません。
6.年間の合計所得が48万円を超えていて133万円以下であること
パート主婦が夫の扶養に入る場合、妻の合計所得が48万を超えていて133万円以下であれば、夫は控除の対象となります※9。
収入に換算すると、給与収入のみの場合は年収が103万円超~201万円以下の間。
対象となる金額の幅が広いので、妻が平日にがっつりパートをしていても控除を受けられる可能性は高いですね。
配偶者特別控除ではいくら控除される?

配偶者控除は夫の合計所得で控除額が変動しますが、配偶者特別控除は夫の合計所得と妻の合計所得の組み合わせで控除額が変動します。
詳しい金額は次の表のとおり※5 ※9。
| 配偶者の 合計所得 |
目安の給与収入 | 扶養する人の合計所得 | ||
|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円 ~950万円 |
950万円 ~1000万円 |
||
| 48万円~95万円 | 103万円~150万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円~100万円 | 150万円~155万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円~105万円 | 155万円~160万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円~110万円 | 160万円~166万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円~115万円 | 167万円~175万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円~120万円 | 175万円~182万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円~125万円 | 183万円~190万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円~130万円 | 190万円~197万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円~133万円 | 198万円~201万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
目安の給与収入は、収入が給与収入のみの場合の年収になります。
扶養される妻の合計所得が48万円~95万円の間の控除額は、配偶者控除と全く同じ金額になっています。
配偶者控除を受けた場合と異なるのは、合計所得が48万円を超えてしまうため、妻の所得税がかかるようになるという点です※4。
合計所得が95万円を超えると、その後は5万円上がるごとに、控除額が下がっていきます。
パート主婦の場合、働き方次第で控除額が大きく変化しますので、注意が必要です!
社会保険における扶養

パートが加入しなければならない条件は?
扶養の対象となる健康保険と厚生年金保険の2つの保険は、一定の条件を満たすとパートであっても加入しなければならず、扶養に入ることができなくなります。
まずはその条件に当てはまっていないか、確認しましょう。
条件その1
パートでも、正社員と同じように常用的な雇用関係にある場合は、健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。
具体的な条件は次のようになります※6。
- 健康保険・厚生年金保険が適用される事業所に雇用されていること
- 1週間の所定労働時間と1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務をしている一般社員の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上であること
この条件に当てはまっていると、扶養に入ることができません。
所定労働時間・所定労働日数とは、雇用された際の労働契約や、その会社の就業規則によってあらかじめ決められた労働時間・労働日数のことです。
繁忙期にいつもより多く働いた、という場合は当てはまりませんので、加入の必要はありません。
条件その2
所定労働時間・所定労働日数が4分の3未満のパートであっても、健康保険と厚生年金保険に加入する必要がある場合があります。
具体的な条件は次のようになります※6。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上を見込まれていること
- 賃金の月額が8万8000円以上であること
- 学生でないこと
- 常時501人以上の企業に勤めていること
3の月額8万8000円以上とは、労働契約によって定められた金額を指します。
また、この金額には通勤手当や残業手当などの手当は含まないのがポイントの一つ。
月額8万8000円を年収に換算すると106万円になることから、しばしば「106万の壁」なんて言われることも。
この5つの条件を全て満たす場合は、パートであっても健康保険と厚生年金保険へ加入しなければならず、扶養に入ることはできませんので、しっかり注意しましょう。
社会保険の扶養に入るには

パートの加入条件にあてはまらなくても、まだ扶養に入れると決まったわけではありません。
扶養に入るためには更に条件があるのです。
健康保険と厚生年金保険それぞれで、扶養に入る条件と、扶養に入るとどんな待遇があるのか、ご説明します。
健康保険
健康保険で扶養に入るための条件は、扶養する夫と扶養される妻が同居であるか、別居であるかで異なります。
具体的には次のようになります※7。
【同居の場合】
年間収入が130万円未満であり、扶養する人の年間収入の2分の1未満であること
【別居の場合】
年間収入が130万円未満であり、扶養する人からの仕送り額未満であること
年間収入とは、扶養に入った日からの1年間の年収の見込みを指します。
これまでの収入をもとに、扶養に入った後も収入が130万円未満であるかどうかを判断します。
この年間収入は、通勤手当などの会社から支払われる賃金全てを含めたものになりますので注意が必要です。
健康保険の扶養に入ることができれば、扶養する夫の健康保険に「被扶養者」として加入することになります。
この時の被扶養者の保険料は免除されます。
また、被扶養者になると、扶養する人の会社を通じて健康保険証を貰い、病院を3割負担で受診することができます。
厚生年金保険
厚生年金保険で扶養に入るための条件は、健康保険と全く同じです※8。
厚生年金保険で夫の扶養に入ることができれば、妻は「国民年金第3号被保険者」として国民年金に加入することになります。
この際、妻の国民年金の支払いは免除されます。
一方で注意したいのは、妻は「厚生年金の扶養に入っても、厚生年金に加入したわけではない」ということ。
健康保険については、夫は「被保険者」として、扶養される妻は「被扶養者」として同じ保険に加入します。
一方で厚生年金は、夫は「国民年金第2号被保険者」として、扶養にされる妻は「国民年金第3号被保険者」として国民年金に加入します。
扶養する側と扶養される側で加入する国民年金が異なるため、このような違いが生じるのですね。
扶養に入ることが出来なかったらどうなるの?

「社会保険加入条件に当てはまらず、扶養にも入れなかった…」
そんな場合には、自身で「国民健康保険」と「国民年金」に加入しなければなりません。
どちらもお住いの市・区役所または町・村役場の窓口にて手続きができます。
加入しなければ無保険状態となってしまいますので、急ぎ加入しましょう。
正しい知識でお得な選択を!

扶養に入ることができれば、月々にかかる税金や保険料を安く抑えることができるというメリットがあります。
一方で、正しい知識を知らなければ、知らないうちに損をしてた!なんてこともあるかもしれません。
正しい知識を得て、自身に合った働き方を選びましょう!
転職活動で迷ったら
「しごと計画学校」へ!
あなたの希望を聞いて最適な求人をご紹介♪面接日程の調整・応募書類の添削などのサポートもしています。
「この条件でも正社員で働けますか?」
そんな不安をお持ちの方はぜひ個別相談へお越しください。

しごと計画学校とは?
1人ぼっちで転職活動はさせません!
職場見学や面接にもついて行きます😆
伴走型の転職エージェント
▶履歴書の書き方
▶面接対策
▶見学や面接の日程調整
▶職場見学も一緒に行きます
▶面接もついて行きます
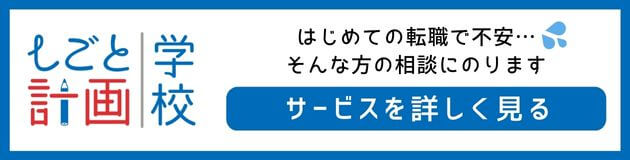
転職・就職セミナーのご案内
主婦の働き方についてもっと知りたい方はこちらもチェック!
【出典】(全て平成30年12月18日閲覧)
※1 国税庁 「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」
※2 国税庁 「No.1191 配偶者控除」
※3 国税庁 「No.1410 給与所得控除」
※4 国税庁 「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」
※5 国税庁 「No.1195 配偶者特別控除」
※6 日本年金機構 「適用事業所と被保険者」
※7 日本年金機構 「健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」
※8 日本年金機構 「国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き」
【注】
※9 令和2年からの所得税控除及び基礎控除の改正に伴い、上記「出典」を令和3年5月18日に再度閲覧し、内容を修正致しました。
しごと計画学校を
利用された方の声
今までしごと計画学校をご利用された方の「利用者の声」転職にまつわるいろんな体験談
しごと計画学校 岡山校 Instagram
▶転職するか悩んでいる
▶載っている求人に応募したい
▶セミナーに参加してみたい
など、DMメッセージも大歓迎です!
LINEで相談もOK
- 非公開求人のご案内
- LINEで転職相談
- 各種予約